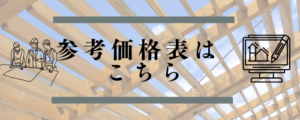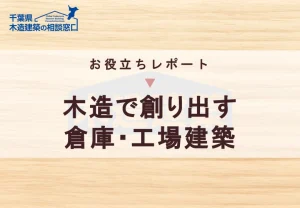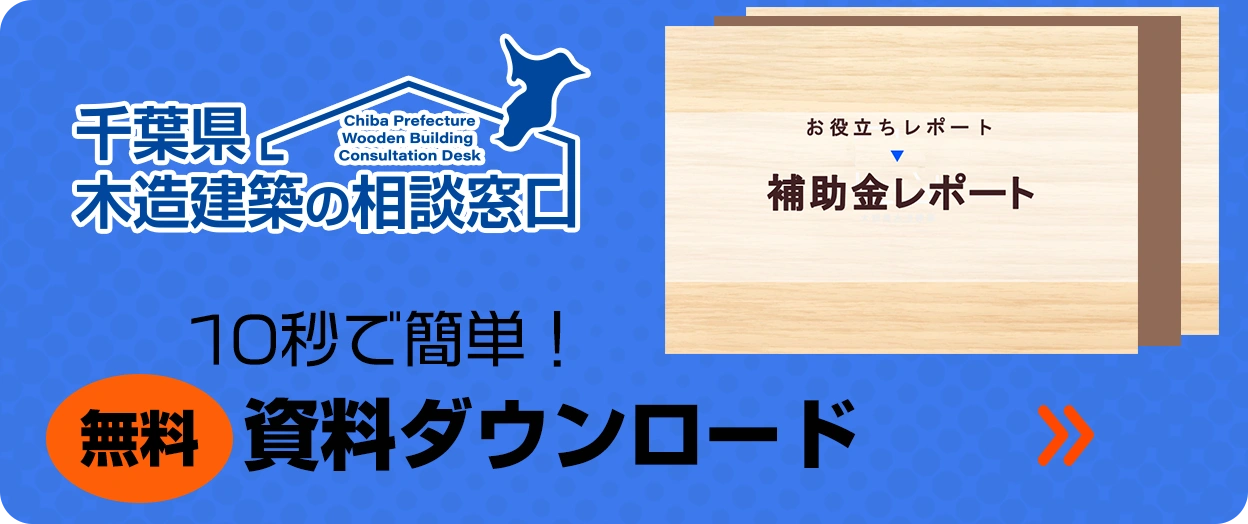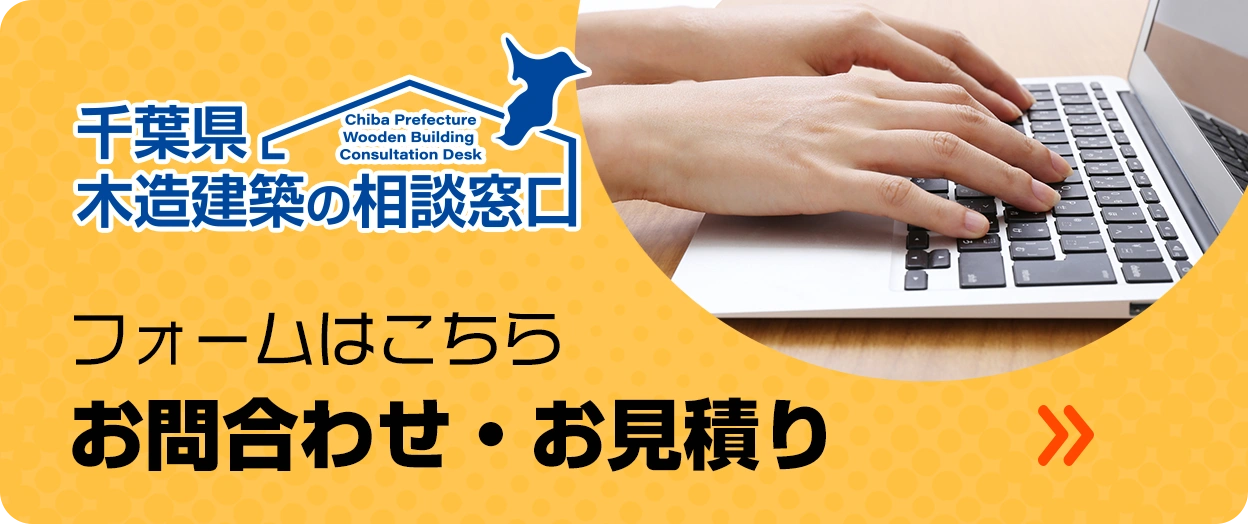お役立ち情報
みなさんこんにちは。大規模木造建築専門ブランドの千葉県木造建築の相談窓口です。
「倉庫を新築したいけど、建設費用は一体いくらかかるのだろう?」「坪単価の相場や費用の内訳が知りたい」「建設費用を少しでも安く抑える方法はないだろうか?」など、倉庫の建設費用に関する様々な疑問やお悩みをお持ちではないでしょうか。
倉庫建設は事業の根幹を支える大きな投資であり、正確な費用感を掴むことがプロジェクト成功の第一歩です。この記事では、2025年の最新データに基づいた倉庫の建設費用と坪単価の相場、費用の詳細な内訳、そしてコストを抑えるための具体的なポイントまで、専門家の視点から網羅的に解説します。さらに、近年注目されている木造倉庫の費用対効果やメリットについても深く掘り下げていきます。
この記事を読むことで、倉庫建設にかかる費用の全体像が明確になり、構造別の坪単価の比較や、予算内で理想の倉庫を建てるための具体的な方法がわかります。
倉庫の新築や建て替えを検討されている経営者様、事業計画を担当されている方、そして賢くコストを管理しながら最適な倉庫を建設したいと考えているすべての方はぜひ最後まで読んでみてください!
倉庫の建設費用を知る第一歩!坪単価の相場を徹底解説
倉庫の建設費用を検討する上で、最も基本的な指標となるのが「坪単価」です。まずは、この坪単価の相場と、構造による費用の違いについて理解を深めましょう。
坪単価とは?倉庫建設費用の基本を理解する
坪単価とは、建物の本体工事費を延床面積(坪数)で割った、1坪あたりの建築コストのことです。例えば、本体工事費が5,000万円で延床面積が100坪の倉庫の場合、坪単価は50万円となります。この坪単価は、大まかな建築費用を把握し、予算計画を立てる際の重要な目安となります。
しかし、注意点として、一般的に坪単価には土地の購入費用や地盤改良費、外構工事費、設計費、空調や電気設備などの付帯工事費、各種申請費用や税金といった諸経費は含まれません。したがって、事業全体の総費用を算出する際には、坪単価で計算した本体工事費にこれらの別途費用を加味する必要があります。
【構造別】倉庫建設の坪単価の相場(2025年版)
倉庫の坪単価は、その建物の構造によって大きく異なります。ここでは、代表的な4つの構造と、それぞれの坪単価の相場をご紹介します。
- 木造(W造): 坪単価の相場は約40万円~80万円です。近年、大規模木造建築の技術が向上し、倉庫や工場でも採用が増えています。断熱性が高く、鉄骨造に比べてコストを抑えられる可能性があるのが大きな特徴です。
- 鉄骨造(S造): 坪単価の相場は約50万円~100万円です。日本の倉庫で最も多く採用されている構造で、設計の自由度が高く、大スパン(柱のない大空間)を実現しやすい点がメリットです。
- 鉄筋コンクリート造(RC造): 坪単価の相場は約80万円~130万円です。耐火性・耐久性・遮音性に非常に優れていますが、コストが高く、工期も長くなる傾向があります。
- テント倉庫: 坪単価の相場は約3万円~15万円と非常に低コストです。短工期で設置できますが、耐久性や断熱性は他の構造に劣り、建築基準法上の制約も多いため、用途が限定されます。

なぜ坪単価に幅があるのか?費用を左右する要因
同じ構造でも坪単価に幅があるのは、建物の仕様や条件によって費用が変動するためです。例えば、建物の形状が複雑であったり、天井高を高くしたり、冷凍・冷蔵設備のような特殊な設備を導入したりすると、坪単価は上昇します。
また、建設地の地盤が軟弱な場合は、地盤改良工事に数百万円単位の追加費用がかかることもあります。都市部では人件費や輸送費が高くなるため、地方に比べて坪単価が高くなる傾向もあります。これらの変動要因を理解し、自社の計画に当てはめて考えることが重要です。
倉庫建設にかかる費用の詳細な内訳
倉庫の建設費用は、「本体工事費」「別途工事費」「諸費用」の3つに大別されます。それぞれの内訳を詳しく見ていきましょう。
本体工事費の内訳
本体工事費は、倉庫の建物そのものを作るための費用です。主に以下の項目が含まれます。
- 仮設工事費: 工事期間中に使用する足場や仮設トイレ、現場事務所などの設置・撤去費用です。
- 基礎工事費: 建物を支える基礎を作るための工事費用。地盤の状態によって費用が変動します。
- 鉄骨・木工事費: 建物の骨格となる柱や梁などの構造躯体を組み立てる費用です。
- 外装工事費: 屋根や外壁、サッシ、シャッターなどの工事費用です。
- 内装工事費: 床、壁、天井の仕上げや、間仕切り壁の設置などにかかる費用です。
- 設備工事費: 電気設備、空調設備、換気設備、給排水設備などの設置費用です。
別途工事費の内訳
別途工事費は、建物本体以外で必要となる工事の費用です。
- 外構工事費: 敷地内の駐車場、アスファルト舗装、フェンス、門扉、植栽などの工事費用です。
- 地盤改良工事費: 建設地の地盤が弱い場合に、建物を安全に支えるために地盤を補強する工事です。
- 既存建物の解体費: 建て替えの場合に、古い建物を解体・撤去するための費用です。
見落としがちな「諸費用」の内訳
建物や工事以外にも、倉庫建設には様々な諸費用が発生します。見落としがちですが、総費用に影響するため、しっかりと予算に組み込んでおく必要があります。
- 設計・監理費: 建築士に支払う設計図面の作成費用や、工事が設計図通りに行われているかを確認する工事監リ費用です。
- 各種申請費用: 建築確認申請や開発許可申請など、行政への手続きにかかる費用です。
- 登記費用・税金: 不動産の所有権保存登記などにかかる登録免許税や、不動産取得税、固定資産税など。
- 保険料: 工事期間中の火災保険や、完成後の火災保険・地震保険料など。
- その他: 地鎮祭などの祭典費用や、近隣への挨拶費用なども考慮しておくと良いでしょう。
倉庫の建設費用を安く抑えるための5つのポイント
多額の投資が必要な倉庫建設だからこそ、費用は賢く抑えたいものです。ここでは、コストダウンを実現するための5つの具体的なポイントをご紹介します。
1. 補助金・助成金制度を最大限に活用する
倉庫建設には、国や地方自治体が実施する様々な補助金・助成金制度を活用できる場合があります。例えば、省エネルギー性能の高い設備を導入する場合の補助金(先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金など)や、事業再構築補助金、ものづくり補助金などが該当する可能性があります。
私自身、お客様の倉庫建設をお手伝いする際には、必ず利用可能な補助金がないか徹底的に調査します。以前、ある中小企業様の案件で、省エネ設備に関する補助金を活用した結果、設備投資費用の3分の1に相当する補助を受けることができ、お客様の負担を大幅に軽減できた経験があります。補助金の情報は非常に重要ですので、必ず専門家に相談しましょう。
2. 倉庫の形状と仕様を最適化する
建物の形状は、建設費用に大きく影響します。凹凸の多い複雑な形状よりも、正方形や長方形といったシンプルな矩形の建物の方が、外壁面積が少なくなり、施工の手間も省けるためコストを抑えられます。
また、内装や設備も、本当に必要な機能を見極め、過剰なスペックにならないように仕様を最適化することが重要です。例えば、保管する商品によっては、高度な空調設備が不要な場合もあります。
3. 【注目】木造建築という選択肢を検討する
倉庫といえば鉄骨造が一般的ですが、近年では木造倉庫がコストパフォーマンスの面で非常に注目されています。前述の通り、木造は鉄骨造に比べて坪単価を抑えられる可能性が高いです。
特に、MOKUPIAが得意とするトラス構造などの技術を用いれば、木造でも柱のない大空間を実現でき、鉄骨造の代替として十分に機能します。加えて、断熱性の高さからランニングコストである光熱費を削減できるメリットもあります。初期費用と運営費用の両面から、木造建築は倉庫のコストを抑える有効な選択肢となります。
4. 複数の建築会社から相見積もりを取る
建設会社によって、得意な工法や部材の調達ルートが異なるため、見積もり金額には差が出ます。必ず複数の会社から見積もりを取り、金額だけでなく、提案内容、工事実績、担当者の対応などを総合的に比較検討することが重要です。
相見積もりを取ることで、適正な価格相場を把握できるだけでなく、各社の強みや提案力を比較し、自社のプロジェクトに最も適したパートナーを見つけることができます。
5. 倉庫建築の実績が豊富な会社に依頼する
倉庫建築には、物流の動線計画や関連法規など、専門的な知識と経験が求められます。倉庫建設の実績が豊富な会社は、コストを抑えつつも機能的な倉庫を実現するためのノウハウを持っています。
過去の施工事例などを確認し、自社が建てたい倉庫に近い実績を持つ会社を選ぶと良いでしょう。経験豊富な会社であれば、設計段階からコストダウンに繋がる様々な提案をしてくれるはずです。
まとめ
倉庫の建設費用は、坪単価の相場を把握した上で、本体工事費、別途工事費、諸費用といった詳細な内訳を積み上げて算出する必要があります。そして、費用を賢く抑えるためには、補助金の活用、設計の最適化、そして適切な建築会社の選定が不可欠です。
特に、これからの倉庫建設において「木造」は非常に魅力的な選択肢です。鉄骨造に代わるコストパフォーマンス、断熱性の高さによるランニングコストの削減、そして環境配慮という時代の要請にも応えることができます。
千葉県木造建築の相談窓口では、大規模木造建築の専門家として、コスト、品質、機能性のすべてにおいてお客様にご満足いただける木造倉庫をご提案いたします。倉庫の建設費用に関するご相談やお見積もり、木造建築の可能性について、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 043-637-1205
043-637-1205